#90 ゼロから学ぶ " 大洲和紙 おおずわし(愛媛県)" の歴史・特徴・魅力・体験場所

大洲和紙(おおずわし)のイメージ薄くてもしなやかで強く、保存性に優れており、漉きムラがないのが特徴
前回は#89 奈良筆(奈良県)について詳しくみてきましたが、今回は大洲和紙について、ひげ先生と おおず君 との会話より、具体的にチェックしてみましょう
スポンサーリンクはじまり
スポンサーリンクおわり

おおず君、よろしくお願いします。ひげ先生こと当ブログの管理人です
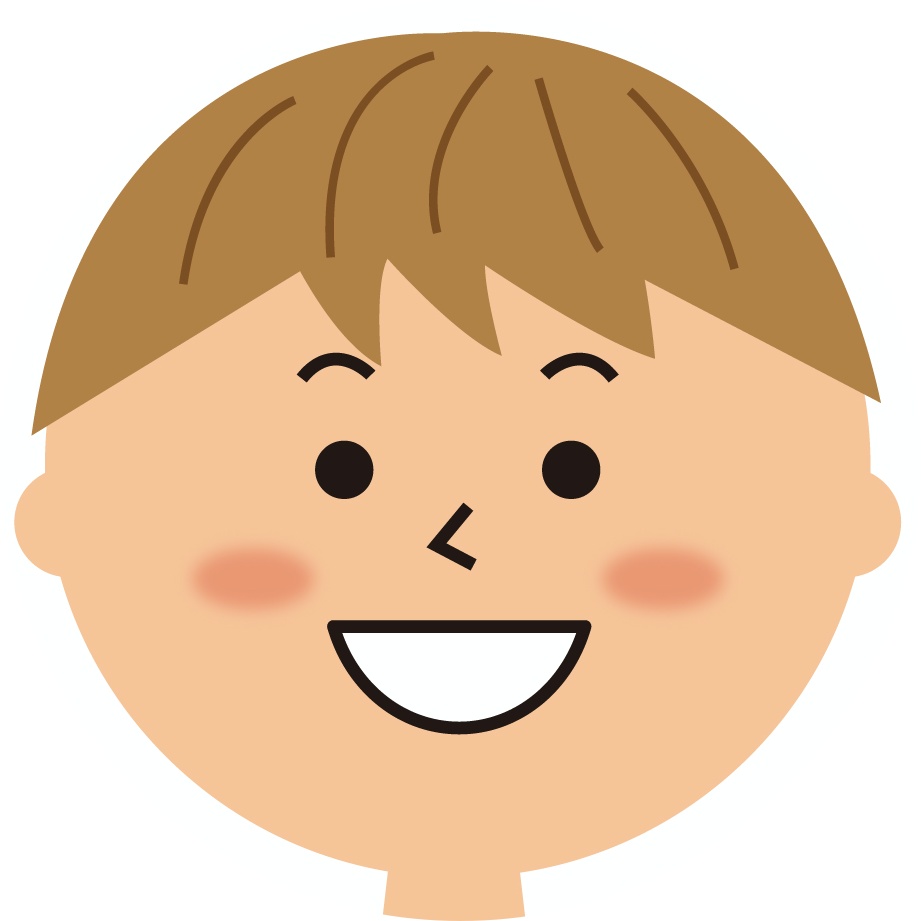
ひげ先生、宜しくおねがいします!
大洲和紙が伝統的工芸品に指定された年月日と産地組合

本日ご紹介の大洲和紙は1977年(昭和52年)10月14日に経済産業大臣より指定を受け、大洲手すき和紙協同組合が産地組合でしたね
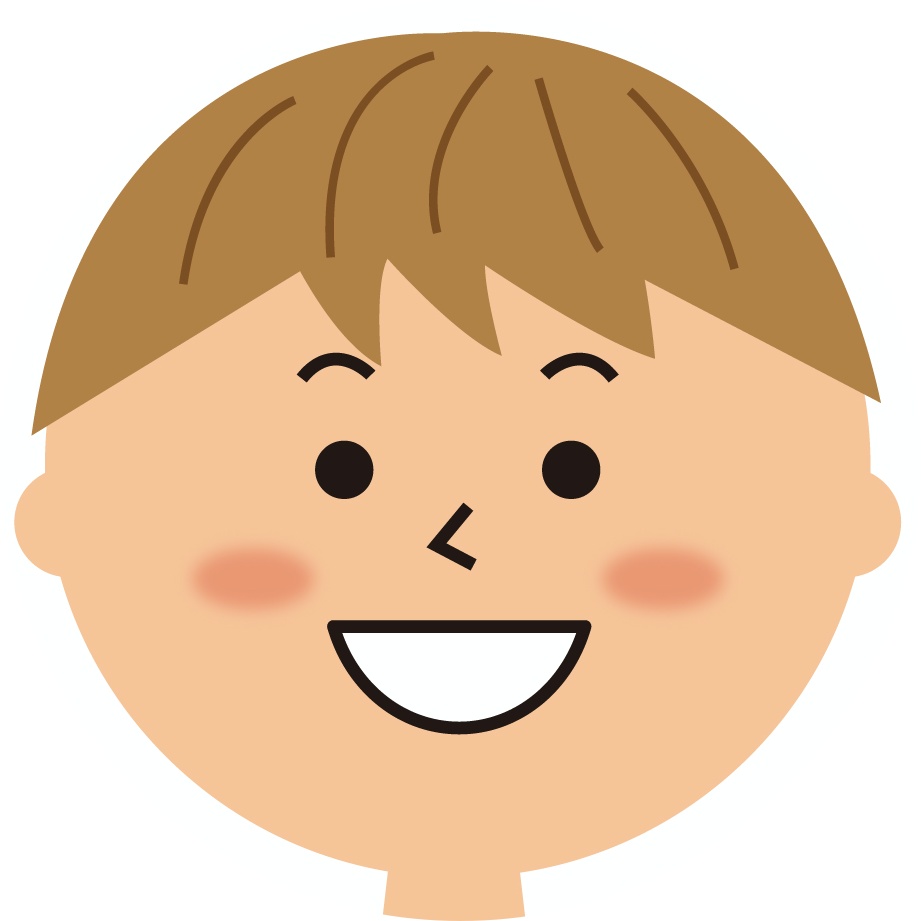
大洲手すき和紙協同組合ですね
大洲和紙の産地組合がある市町村と観光スポット

大洲手すき和紙協同組合は、喜多郡(きたぐん)にあります
喜多郡(きたぐん)とは
愛媛県のほぼ中央部に位置し、松山市から約40Km離れている
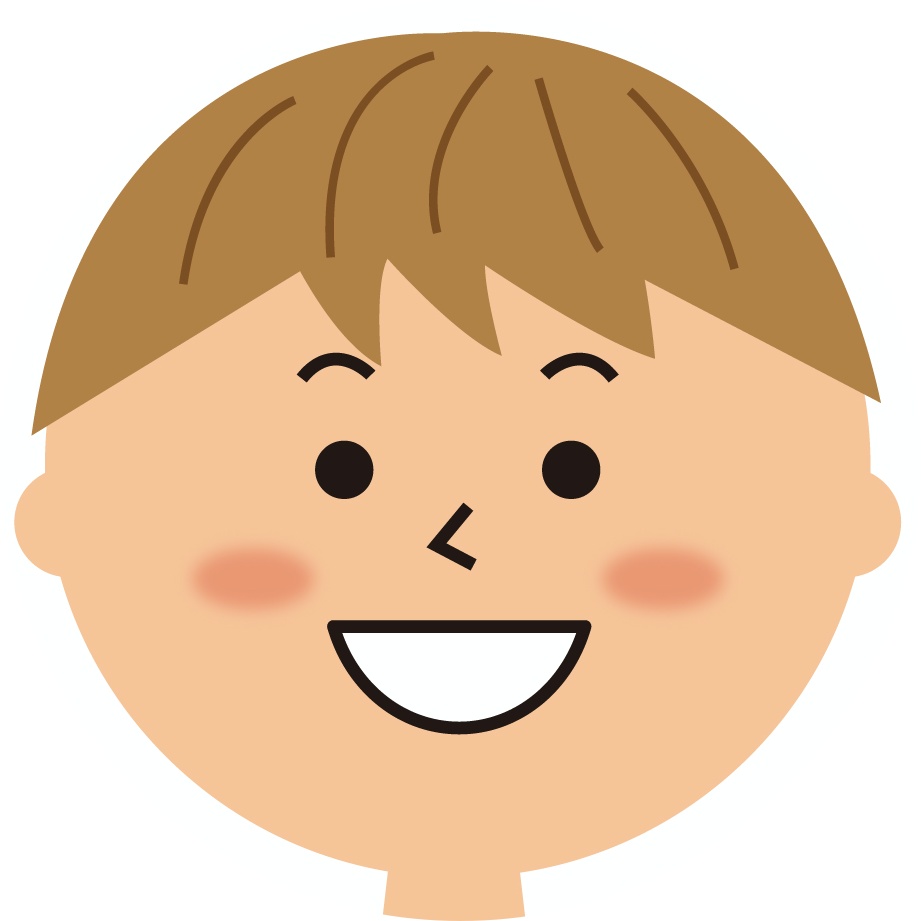
東京からはどのようにして行きますか?

東京から喜多郡への行き方ですが、飛行機+バスがおすすめです
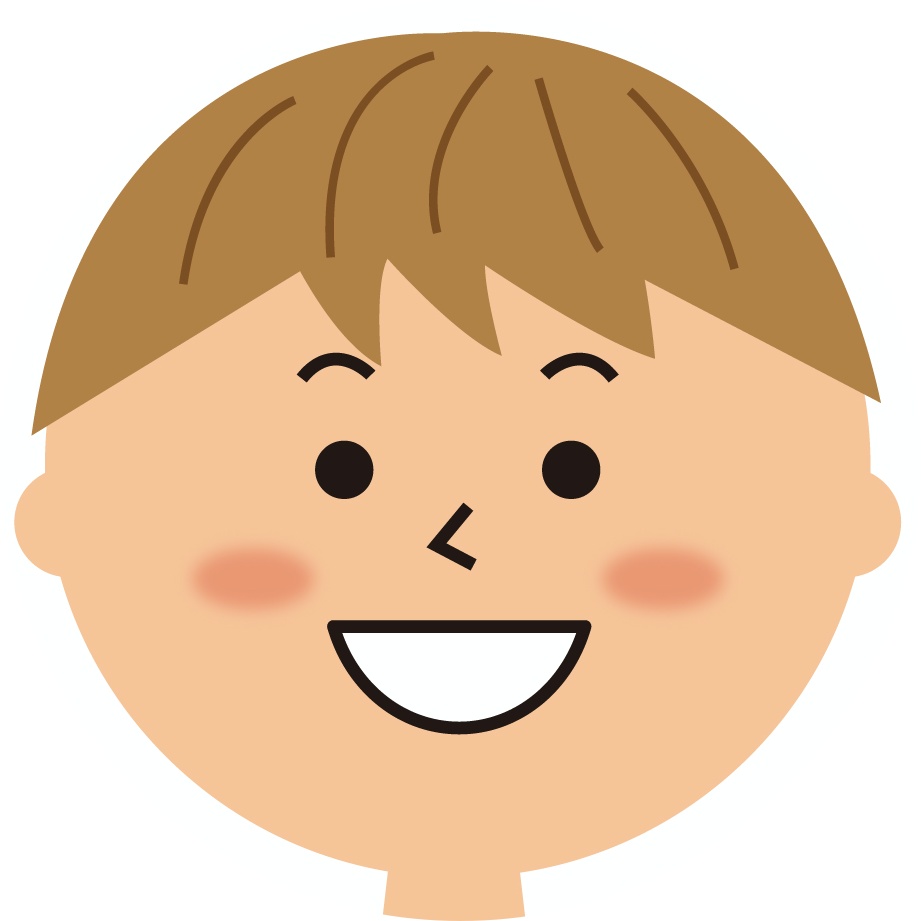
四国エリアだと飛行機がおすすめなのですね

トータル所要時間は約3時間30分で着くことができます
羽田空港 → 松山空港(飛行機:約1時間30分)
松山空港 → 内子インター口(肱南観光バス::約50分)
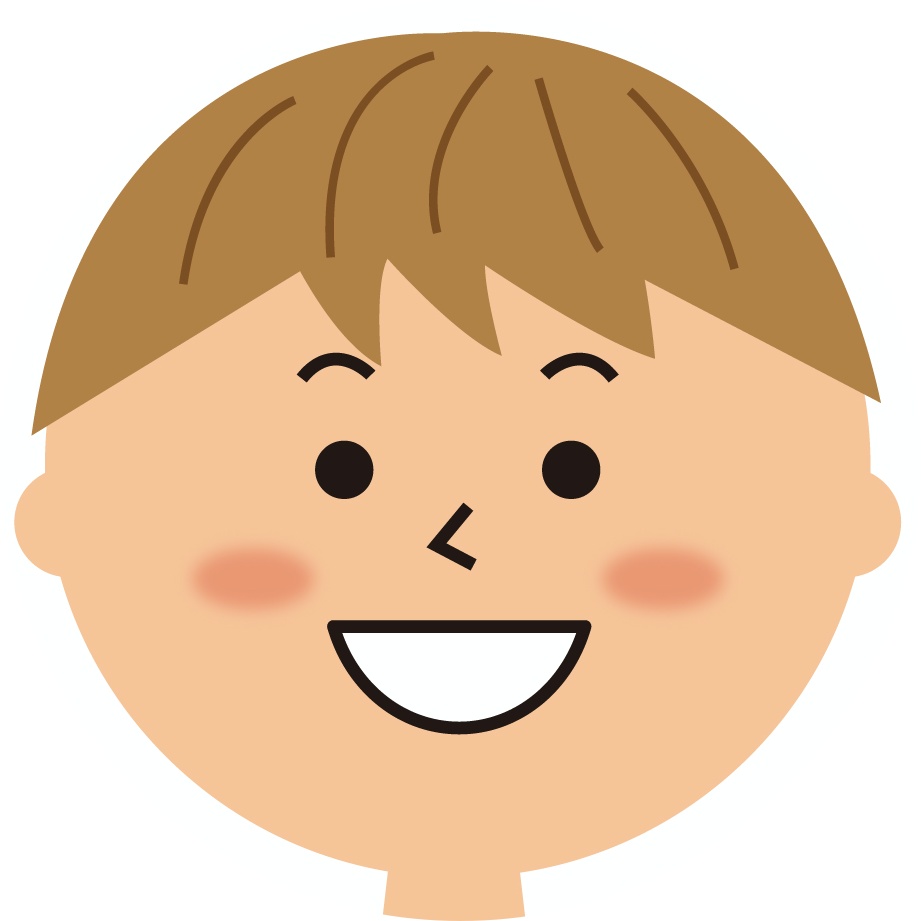
空港からバスが出ているは良いですね

また、喜多郡には、内子座(うちこざ)という観光スポットがあります
内子座(うちこざ)とは
大正から100年続く芝居小屋で、地元の有志によって創建された

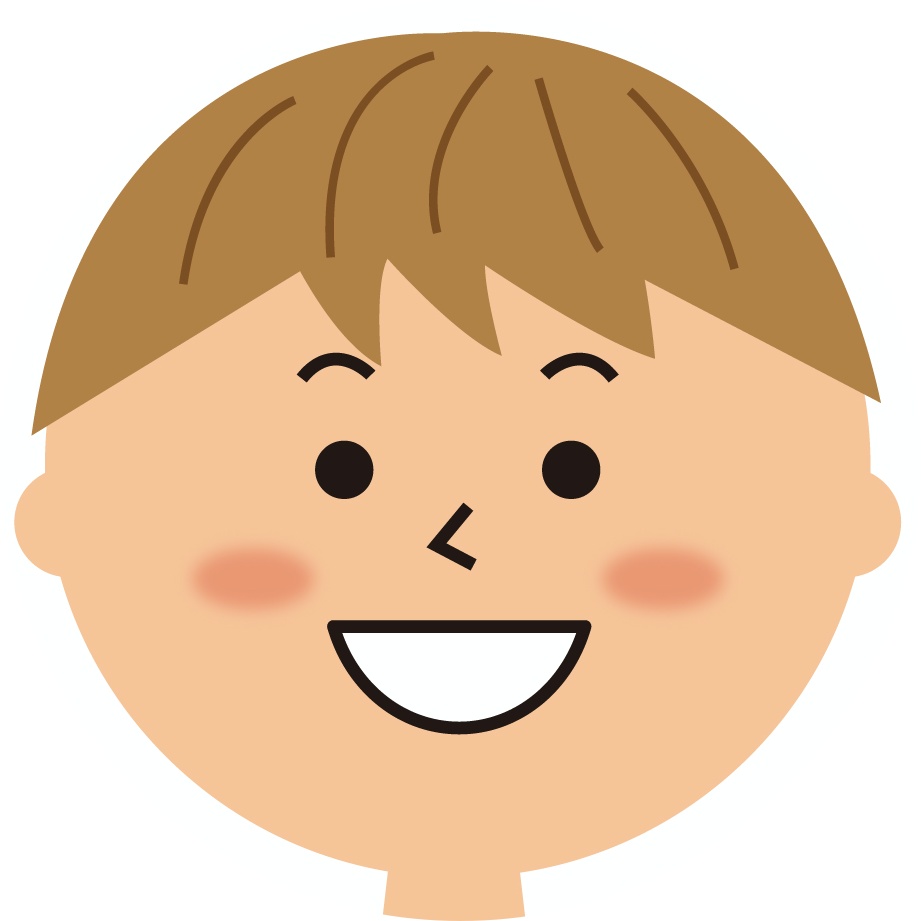
趣のある建屋ですね!
大洲和紙の歴史・特徴・魅力

その内子座(うちこざ)がある喜多郡における、大洲和紙の歴史について見ていきましょう
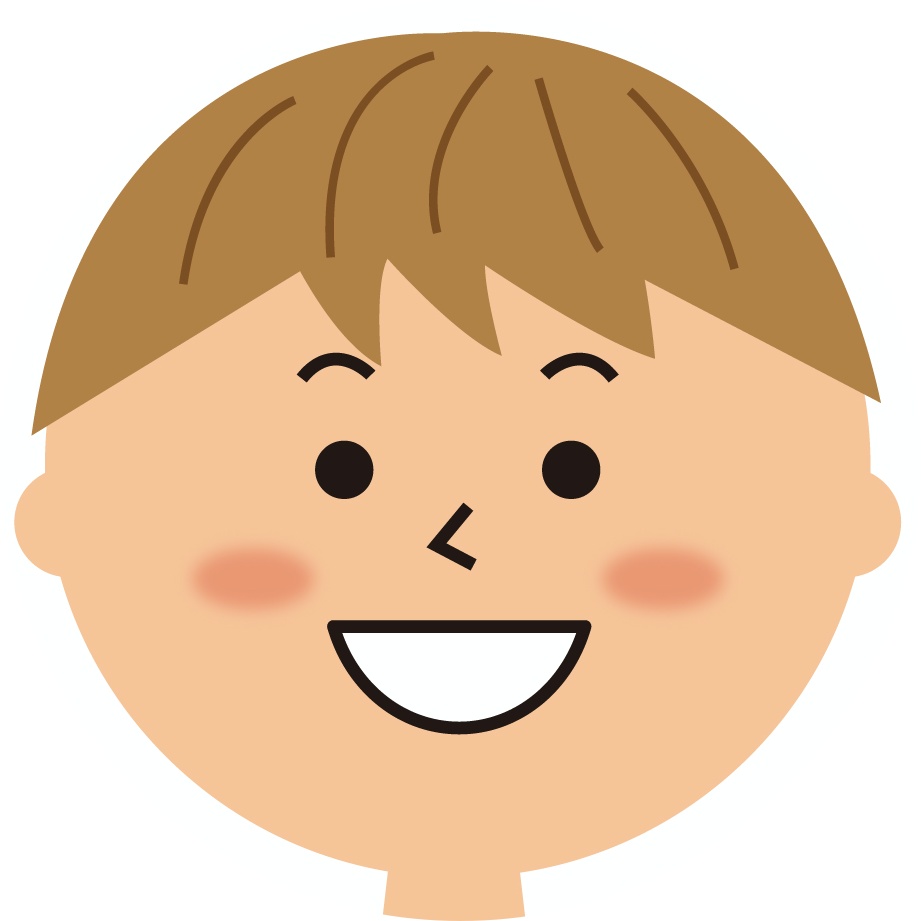
大洲和紙の歴史とは・・・

はじまりは、平安時代といわれ、清流・小田川の水を用いた流し漉き(ながしすき)で紙が作られていました
流し漉き(ながしすき)とは
簀桁(すげた)で和紙の紙料液をすくい、縦横に動かし繊維を絡みあわせる漉き方

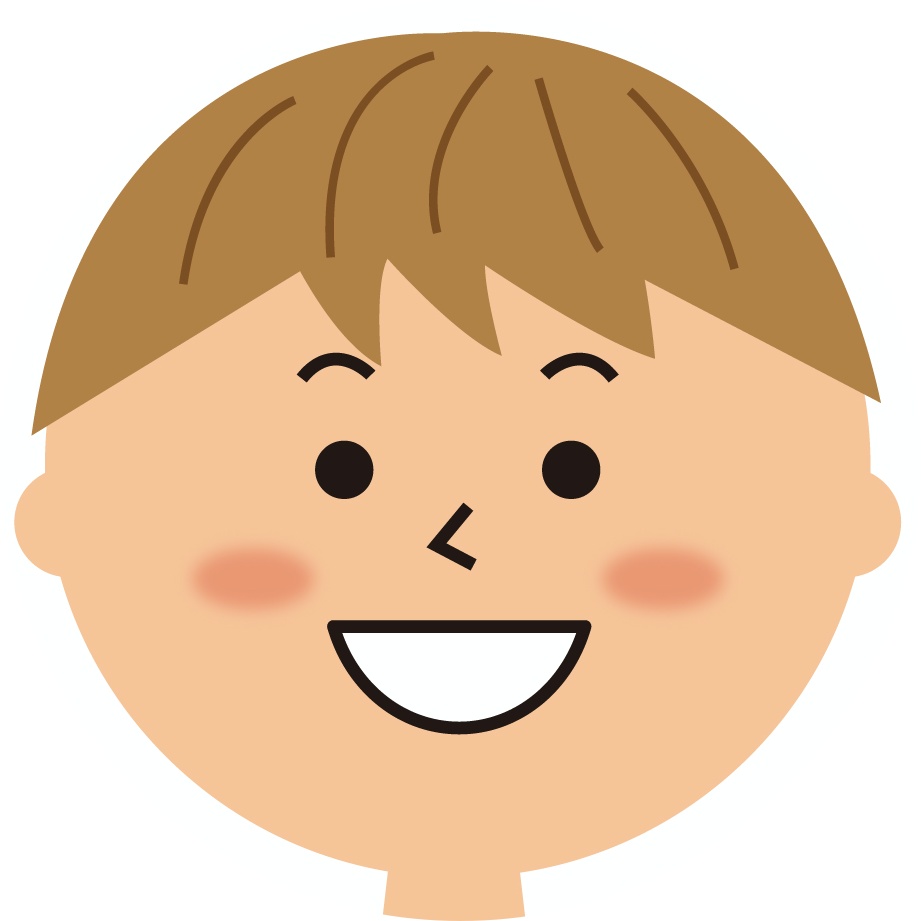
はじまりは平安時代ですか・・長い歴史ですね

「延喜式(えんぎしき)」と呼ばれる書物に、大洲和紙を上納した記録も残っております
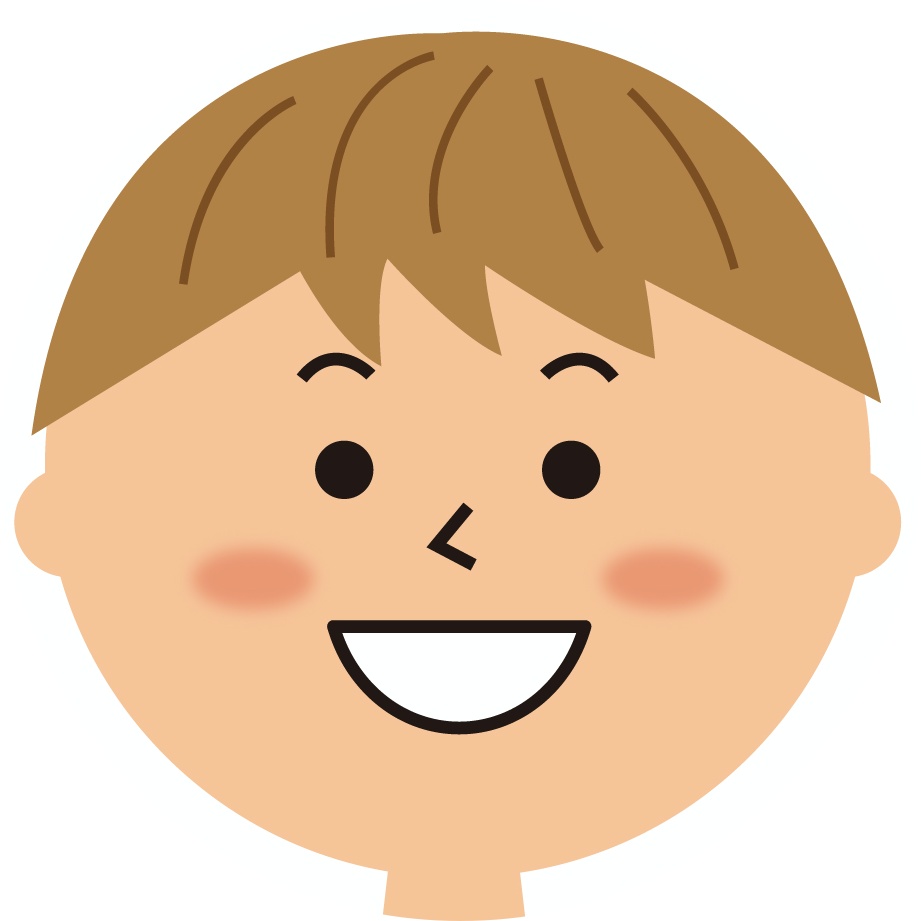
記録も残っているのかぁ

江戸時代には、この地を治めた大洲藩(おおずはん)が保護し、紙漉きの発展を支えてきました
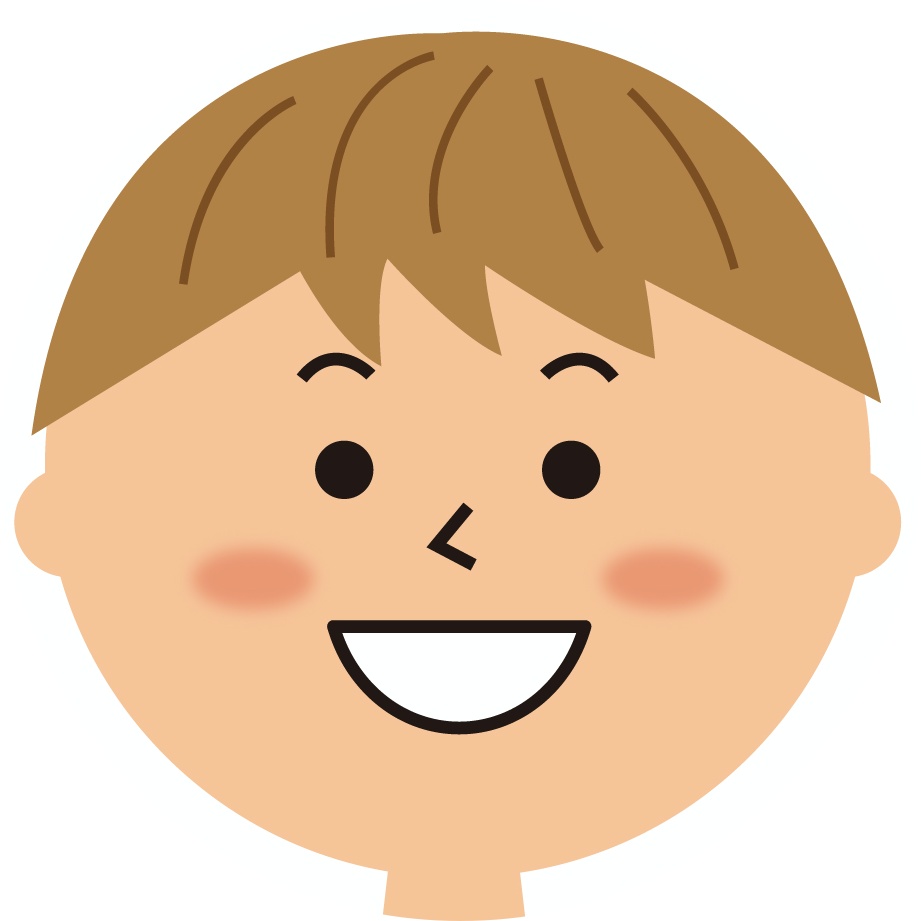
藩も支援をしていたのですね

原料は主にコウゾ・ミツマタ・ガンピなどの木の皮を用いて、原料を煮る蒸煮(じょうしゃ)を行い、叩いて細かい繊維にする叩解(こうかい)、漉いて紙にする抄紙(しょうし)の製造プロセスを経て作られます
コウゾとは
クワ科の落葉低木。繊維は太くて長く強靱

ミツマタとは
ジンチョウゲ科の落葉低木。皮の繊維は細く強い。枝が三つ叉に分かれるところから“ミツマタ”と呼ばれる

ガンピとは
ジンチョウゲ科の落葉低木。優美で光沢があり、透明度もよい

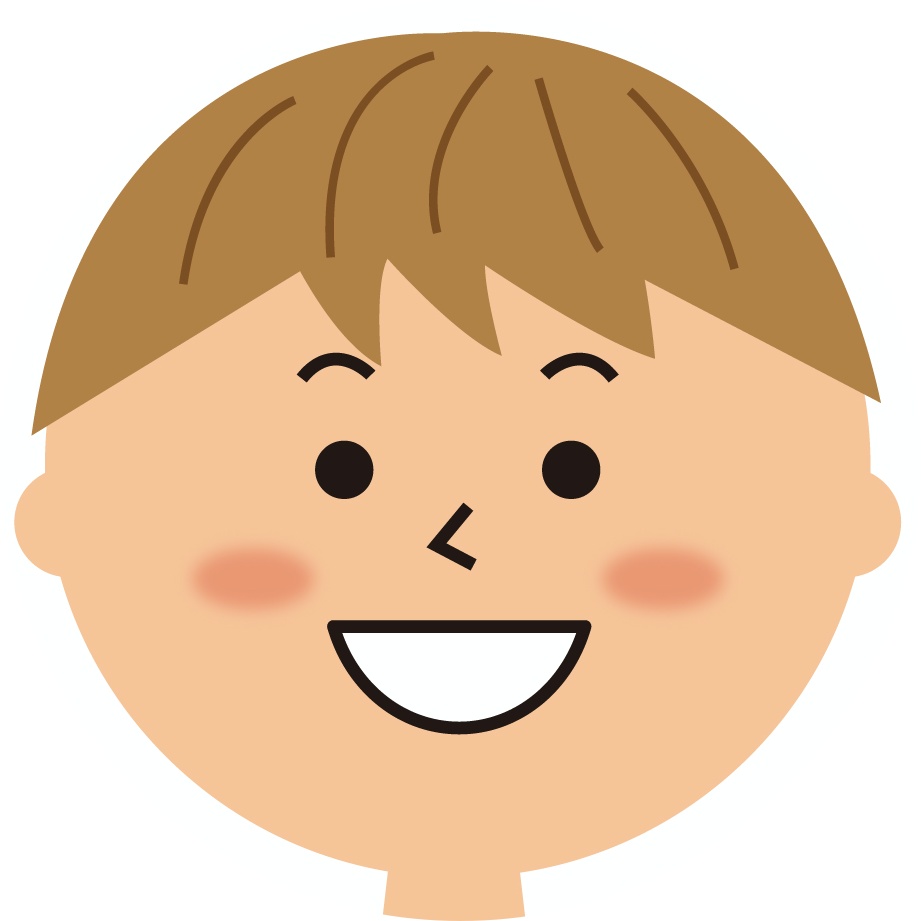
原料として木の皮が使われるのですね

特徴は、薄くて強く漉きムラがないため、書道用紙や障子紙をはじめ、壁紙・版画用紙・色和紙、僧侶が着用する紙の着物である紙子(かみこ)、いかさぎ大凧合戦に貼られる凧紙(たこがみ)にも使用されております
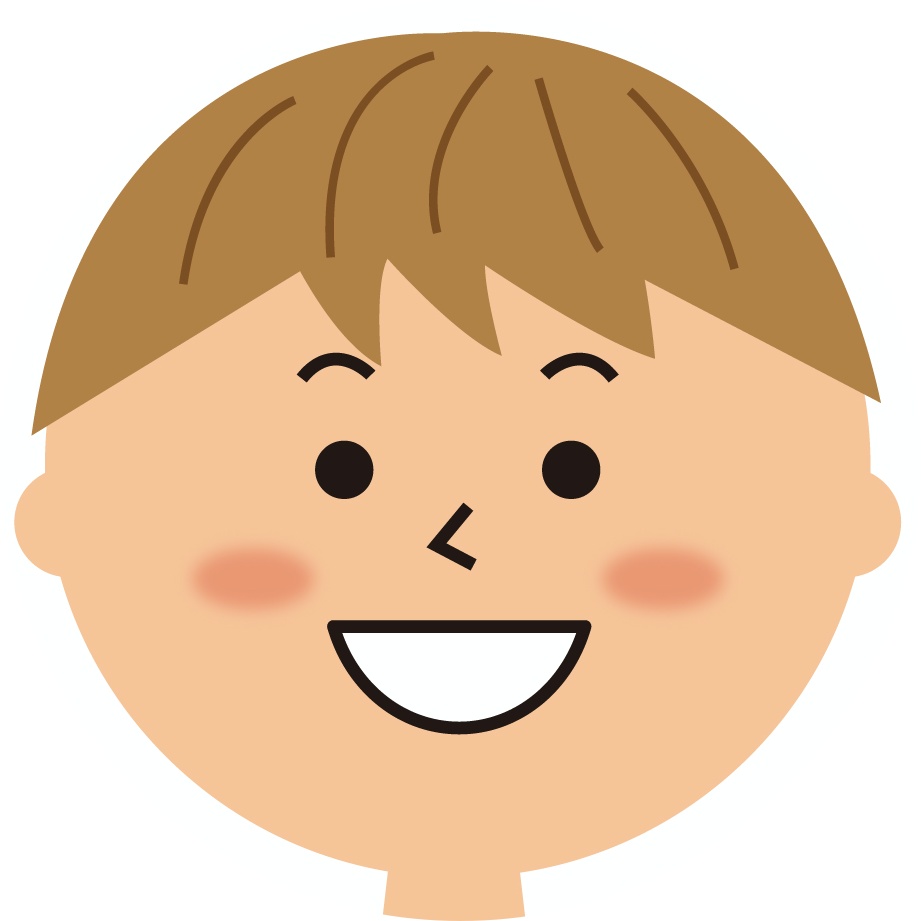
色々な用途に使用されているのですね

今でも伝統的な流し漉きの技法が受け継がれ、1日に1人の職人で100枚以上作られています
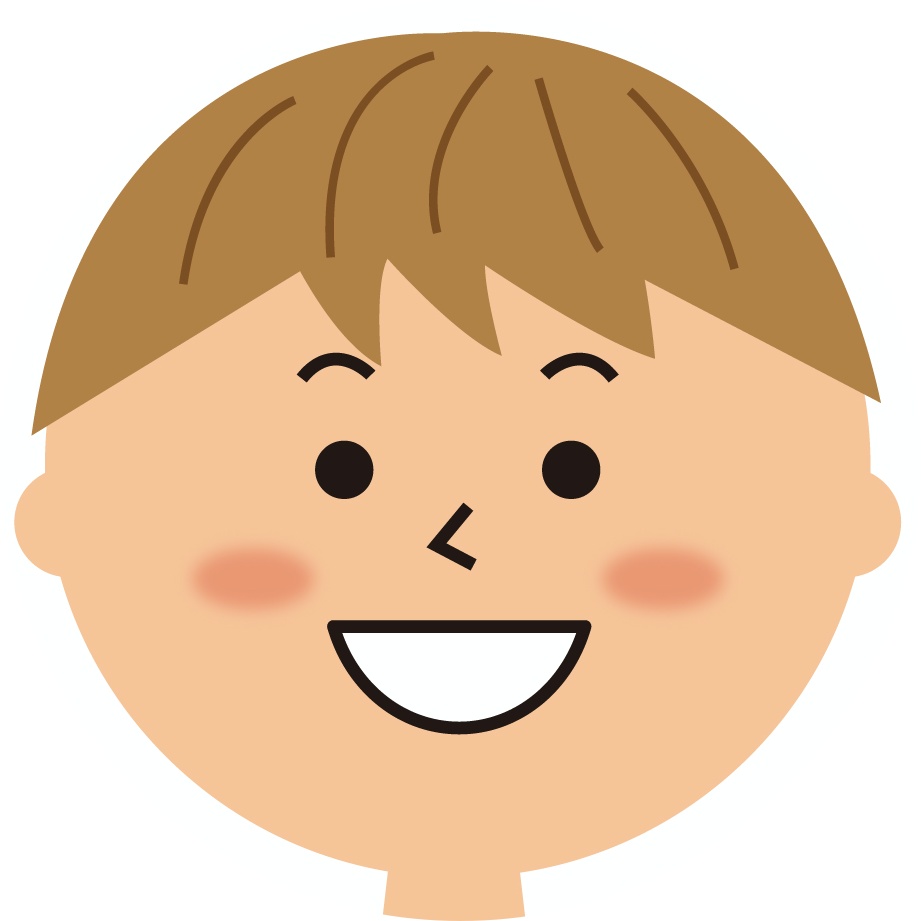
その技術を体験できるところってありますか?

あるよ!是非、体験してみてくださいね!!
大洲和紙の体験場所
| 事業者名 | 内容 | 事業者HP |
| 大洲和紙会館(天神産紙工場) | 見学 紙漉き | https://oozuwashi.business.site/ |
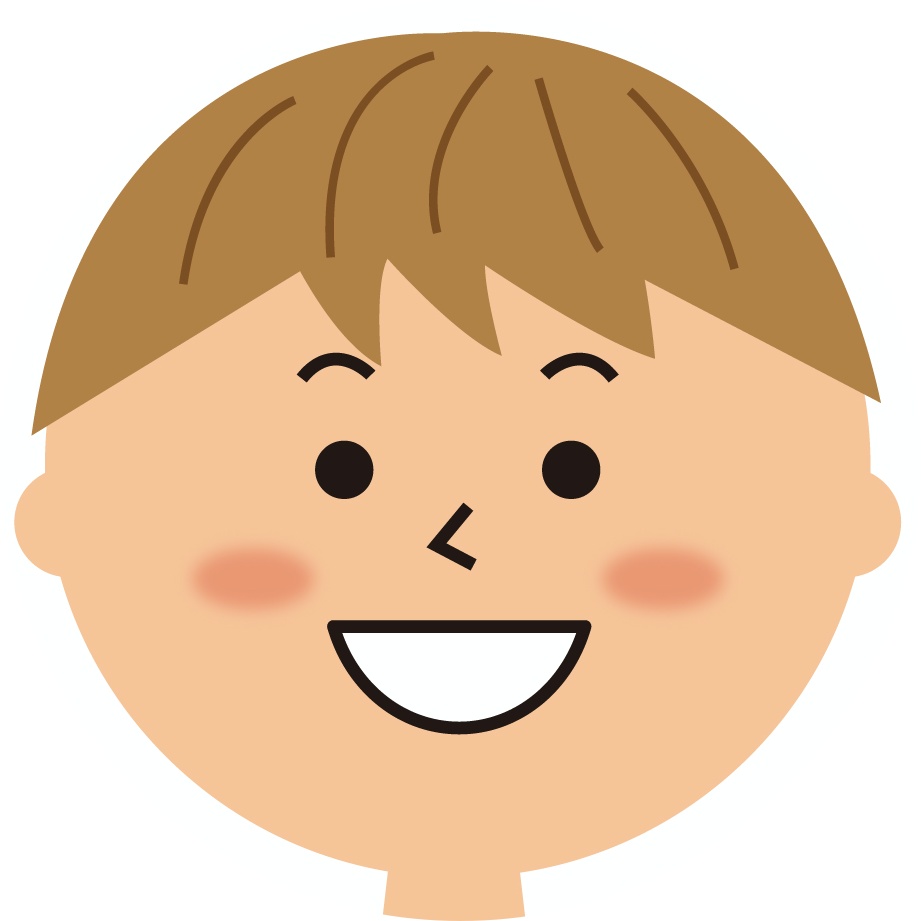
大洲和紙の歴史や工芸体験の情報有難うございました

大洲和紙の“障子紙”が売られていますので良かったらぜひ!
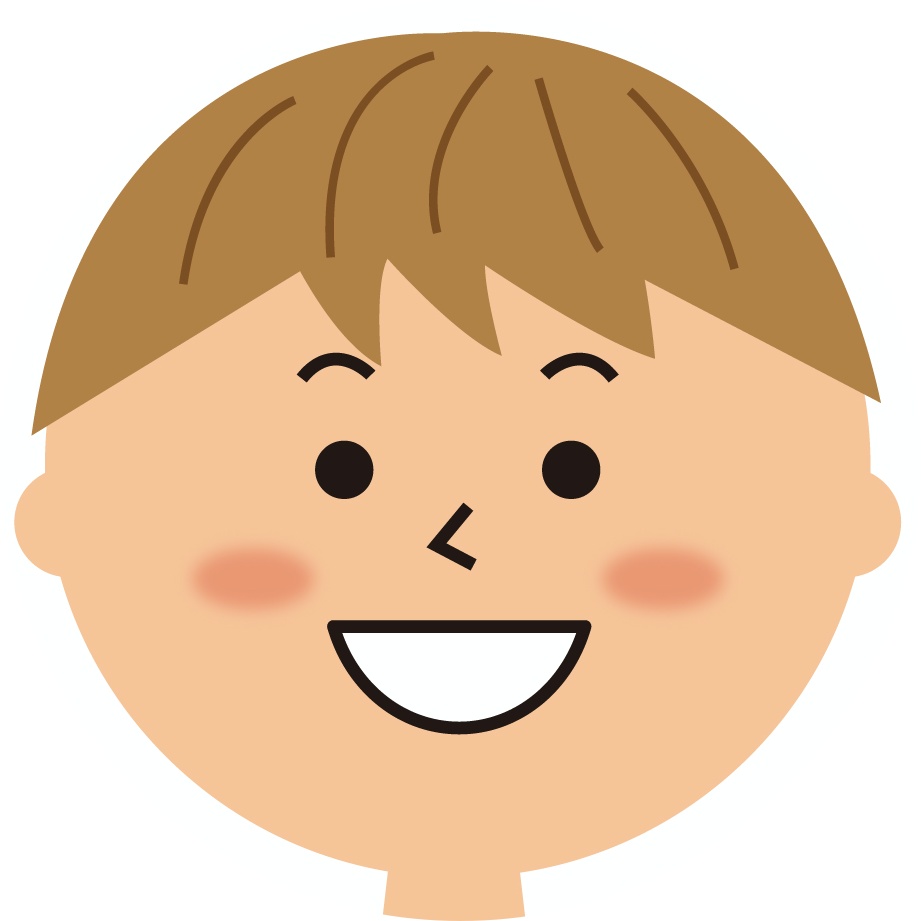
いい手漉き和紙ですね!!

はい、それでは#90 大洲和紙(おおずわし)についてのお話はここまで!
次回は#91 伊万里・有田焼(いまり・ありたやき)を見ていきましょう
(参考)
・47都道府県 伝統工芸百科(丸善出版)
・調べる!47都道府県 伝統工芸で見る日本(同友館)
スポンサーリンクはじまり
スポンサーリンクおわり


