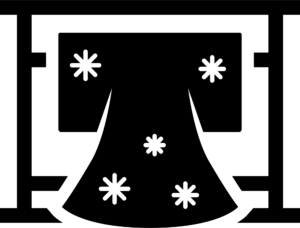#9 ゼロから学ぶ " 本場大島紬 ほんばおおしまつむぎ(鹿児島県・宮崎県)" の歴史・特徴・魅力・体験場所

大島紬は草木染めをした後にどろ染を行い、しぶく光沢のある黒色を生み出す
前回は#8 飛騨春慶(岐阜県)について詳しくみてきましたが、今回は本場大島紬について、ひげ先生としま子ちゃんとの会話より、具体的にチェックしてみましょう
スポンサーリンクはじまり
スポンサーリンクおわり
目次

しま子ちゃん、こんにちは。ひげ先生こと当ブログの管理人です

ひげ先生、よろしくお願いします

それでは今回、鹿児島県・宮崎県の本場大島紬(ほんばおおしまつむぎ)を紹介したいと思います

鹿児島と宮崎県の2県なのですね
本場大島紬が伝統的工芸品に指定された年月日と産地組合

本場大島紬は1975年(昭和50年)2月17日に経済産業大臣より指定を受け、本場奄美大島紬協同組合・本場大島紬織物協同組合が産地組合だったね

鹿児島の中でも本土と奄美大島の両箇所に組合があるのですね
本場大島紬の産地組合がある市町村と観光スポット

産地組合は主に奄美市(あまみし)と鹿児島市(かごしまし)にあるよ
奄美市(あまみし)とは
鹿児島県の南西諸島中央部、奄美群島の奄美大島に位置する

奄美市ではあやまる岬観光公園が有名スポットですね
あやまる岬観光公園とは
奄美十景にも数えられる景勝地(けいしょうち)であり、岬からはさんご礁の海が一望でできる場所

鹿児島市(かごしまし)とは
鹿児島県の中部に位置する市で、鹿児島県の県庁所在地

鹿児島市といえば桜島(さくらじま)ですね
桜島(さくらじま)とは
標高約1,117メートルの御岳(北岳)という活火山が、現在も活発に噴火を続けている


絶景が見られるのですね
本場大島紬の歴史・特徴・魅力

それでは本場大島紬の歴史を見てみましょう

気になります!

本場大島紬のはじまりは古く、1300年前とも言われています

だいぶ昔からあるのですね

その中でも盛んになったのは、江戸時代中期の18世紀初めになります

18世紀は1700年代ですね

鹿児島は薩摩藩が統治していたのですが、島民のつむぎ着用を禁止されておりました

高級品だったからですね

そうですね!上質な繭の糸を用いる別格の風合いが、高級織物として上納品(じょうのうひん)に定められておりました。
上納品(じょうのうひん)とは
上下関係のある組織について、 下位の組織から、上位の組織に対して品物を渡すこと
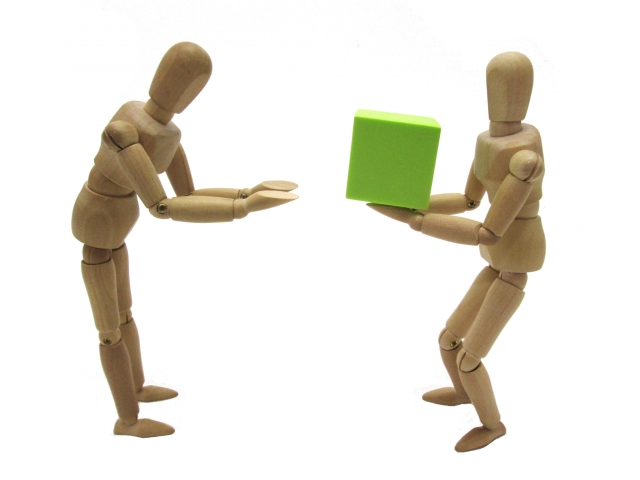

年貢と一緒ですね

生糸の光沢と軽い風合い、自在な絵柄と染色法の技法に特徴があります

どういった特徴ですか?

柄を染め分けるための締機(しめばた)という技法から生み出される、とても細かなかすり模様です

締機(しめばた)って何ですか?

それまで手でくくっていた絣(かすり)を、機織りのような原理で機を使ってくくるようになりました。
絣(かすり)とは
糸のところどころをくくり、白く残して染めた〈かすり糸〉で織った柄のこと


他に何か特徴はありますか?

島の泥と植物との化学反応を利用した“泥染め”は世界的にもめずらしい染め方です
泥染め(どろぞめ)とは
世界で唯一、奄美大島でのみ行われている天然の染色技法


泥で染める発想が驚きですね

島に多いソテツという木やハブのうろこを参考にした複雑な模様が生まれました
ソテツとは
裸子植物ソテツ科の常緑低木


よく鹿児島で見る木ですね

複雑な柄が多いため着物1着を織り上げるのに、1ヶ月から数ヶ月かかります

1着でそんなに時間がかかるんですね。最高級品と呼ばれるのがよく分かります

この本場大島紬は世界三代織物の一つとされております

他の織物はどういった織物ですか?

フランスのゴブラン織、トルコ・イランのペルシャ絨毯です

世界的に有名なものですね!

ただ本場大島紬は着物の需要が減ってしまっているので、時代に合わせた商品作りが必要になっているんだよ

その技術を体験できるところはありますか?

あるよ!是非、体験してみてくださいね!!
本場大島紬の体験場所
| 事業者名 | 内容 | 事業者HP |
| 夢おりの郷 | 泥染め・藍染体験、機織り体験 | https://www.yumeorinosato.com/ |
| 大島紬村 | 泥染め・藍染体験 | http://www.tumugi.co.jp/infomation/experience.html |
| PONGEE(ポンジー) | 機織り体験、大島紬ペン作り体験 | https://www.oose1930.co.jp/experience/ |

ぜひ体験してみたいわぁ

本場大島紬の“反物”が売られていますので良かったらぜひ!

本場大島紬の着物着てみたいなぁ

はい、それでは#9 本場大島紬(ほんばおおしまつむぎ)についてのお話はここまで
次回は#10 久米島紬(くめじまつむぎ)を見ていきましょう
(参考)
47都道府県・伝統工芸百科(丸善出版)
調べる!47都道府県 伝統工芸で見る日本(同友館)
伝統工芸のきほん2 布(理論社)
スポンサーリンクはじまり
スポンサーリンクおわり